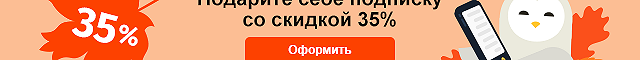
第六章
ガレスは自室の中で歩きながら、剣を持ち上げる儀式の失敗にぼう然として頭が混乱し、その影響について整理しようとしていた。ショックで麻痺したようになっていた。マッギル家の者が七世代にもわたって誰も振り上げられなかった運命の剣。それを試そうとした自分の愚かさが信じられなかった。なぜ、自分が先祖たちよりも優れているだろうと考えたのだろうか?なぜ自分だけは違うと?
もっとよくわかっておくべきだった。慎重になり、自分を過大評価するべきではなかった。父の王座を受け継いだことに満足していればよかった。なぜそれをもっと無理に進めようとしたのだろうか?
臣民はもはや自分が選ばれし者でないことを知っている。そのことで彼の支配に傷がつくうえ、恐らく父の死に関して自分に疑いを持つ根拠が増えただろう。皆が自分のことを違う目で見始めていることに気付いていた。まるで自分が生霊で、彼らが次の王を迎える準備をしているかのように。
更にひどいのは、生まれて初めて自分に自信が持てなくなったことだった。今まで、自分の運命をはっきりと見据えてきた。父の後を継ぐ運命にあると確信してきたのだ。統治し、剣を振りかざすものだと。その自信が根底から揺らいだ。今は何も確信できなかった。
そして最悪なことに、剣を持ち上げようとした瞬間に見た父の顔がずっと目に浮かぶのだった。これは父の復讐なのだろうか?
「お見事ね」低く、皮肉な響きを持った声がした。
ガレスは、部屋に誰かいたのかと衝撃を受けて振り向いた。その声で誰かすぐにわかった。長年聞き慣れ、自分がさげすんできた妻の声。
ヘレナだ。
部屋の向こうの隅に立ち、アヘンのパイプを吸いながら自分を観察していた。深く息を吸って止め、ゆっくりと吐き出した。目は充血し、長時間吸い過ぎていることがわかった。
「ここで何をしている?」ガレスが尋ねた。
「ここは私の花嫁時代の部屋よ」彼女が答えた。「ここでは好きなことができるわ。私はあなたの妻でもあり、女王なんですから。忘れないでちょうだい。あなたと同じく私もこの国を支配しているのよ。そして今日あなたが失敗した以上、統治という言葉はあまり厳密には使わないようにするわ」
ガレスは顔が赤くなった。ヘレナはいつでも最も人をさげすむやり方で打ちのめしてくる。しかも一番不都合な時に。ガレスは彼女をどの女よりも軽蔑していた。結婚しようと決めたことが信じられなかった。
「そうなのか?」ガレスは振り向いてヘレナのほうへ向かって行きながら、怒りではらわたが煮えくり返る思いで言った。「お前は私が王であることを忘れている。妻であろうがなかろうが、他の者と同じようにお前を投獄することだってできるのだぞ」
ヘレナは軽蔑したように彼を鼻で笑い、
「それから?」と鋭く言った。「国民にあなたの性的嗜好を疑わせる?策略を練るガレスなら、そうはさせないでしょうね。人が自分のことをどう見るか誰よりも気にする人だもの」
ガレスはヘレナを前にして口をつぐんだ。自分を見透かす方法を心得ているとわかり、心からうとましく思った。彼女の脅しを理解して議論しても良いことはないと悟り、ただこぶしを握り締めて静かに立ち尽くすだけだった。.
「何が望みだ?」ガレスはあわてないように、と自分を制しながらゆっくりと聞いた。「私から何か引き出そうというのでない限りここへは来ないだろう」
ヘレナは乾いた嘲笑を浮かべた。
「私は欲しいものは何でも自分で手に入れるわ。あなたに何か要求しようと思って来たんじゃなくて、言おうと思ったことがあって来たの。剣を振り上げるのに失敗したのを皆が見たでしょう。それで私たちはどうなったかしら?」
「私たち、っていうのはどういう意味だ?」ガレスがヘレナの思惑をいぶかりながら聞いた。
「私がずっと前から知っていたことが、今や国民にもわかったということよ。つまりあなたが選ばれし者なんかじゃなくて、落伍者だってこと。おめでとう。今じゃ正式に知られたわけね」
ガレスが睨み返した。
「父も剣を振りそこなった。それで王として国を立派に治めることができなかったわけじゃない」
「でも王としての威厳には影響があったわ」ヘレナがピシャリと言う。「どんな時にもね」
「私の能力のなさに不満があるなら」ガレスが憤って言う。「ここからいなくなったらどうだ?私など置いて行きたまえ!結婚のまねごとなどやめればよいのだ。私は今や王だ。お前は必要ない」
「そのことを話題にしてくれてよかった」ヘレナが言った。「それがここに来た理由だから。結婚を終わらせて、正式に離婚したいの。好きな人がいるのよ。本物の男性よ。あなたの騎士の一人、戦士で、私が経験したことがないほど、私たちは本気で愛し合っているのよ。この関係を秘密にしておくのはもうやめにして、公にしたいの。そして彼と結婚したいので、離婚してください」
ガレスは衝撃を受けて彼女のほうを見た。胸に短剣を刺されたばかりのように、心に穴を開けられたような気がした。なぜヘレナは公にしなければならないのか?よりによって、なぜ今なのか? もうたくさんだった。自分が弱っているときに、よってたかって蹴られているかのようだった。
それにもかかわらず、ガレスは自分がヘレナに対して深い思いを抱いていたと気づき自分でも驚いた。彼女が離婚を迫ったとき、衝撃を受けたからである。ガレスは気が動転した。意外なことに、自分が離婚を望んでいないことに気付いた。自分から求めたのであれば、それはよかった。だが、ヘレナから切り出された場合は別問題だ。そう簡単に彼女の好きにさせたくはなかった。
まず第一に、離婚が王としての威厳にどう影響するかと考えた。国王が離婚したとなると多くの疑問が生じる。また、自分の意思に反してその騎士に嫉妬を覚えた。自分に面と向かって男性らしさの欠如を持ち出したのも憎らしかった。二人に仕返しをしたかった。
「そうはさせない」ガレスは切り返した。「お前は永遠に私の妻として縛られているのだ。決して自由にはさせない。そしてお前が通じていた騎士にもし出会ったなら、拷問にかけて処刑する」
ヘレナが怒鳴るように言った。
「私はあなたの妻なんかじゃないわ!あなたも私の夫などではない。あなたは男じゃないんですもの。私たちの結婚は初日からひどいものだった。権力のための政略結婚だったのよ。何もかも反吐が出るようなことだった。いつでもね。真の結婚をする私の唯一のチャンスが台無しになったのよ」
怒りが沸騰したヘレナが一息ついた。
「離婚してくれなければ、あなたの正体を王国中にばらすわ。どうするかはあなたが決めて」
そう言うとヘレナはガレスに背を向け、部屋を横切り、開いた扉から出て行った。扉を閉めようともしなかった。
ガレスは石造りの部屋に一人たたずみ、ヘレナの足音がこだまするのを聞いていた。ふるい落とすことのできない寒気を感じていた。すがれる確かなものはもう何もないのだろうか?
ガレスは開いたままの扉のほうに目をやり、震えながら立ちすくんでいたが、誰か別の者が入って来るのを見て驚いた。 ヘレナとの会話を、脅しを整理する間もなく、ファースの見慣れた顔が入って来た。申し訳なさそうな表情でためらいがちに部屋に入ってくる彼に、普段の弾む足取りは見られなかった。
「ガレスかい?」ファースは自信なさそうな声で尋ねた。
目を見開いてガレスを見ながら、心苦しい様子でいるのがガレスにもわかった。そのほうが良いんだ、ガレスはそう思った。 ガレスに剣を振り上げるよう仕向けて決心させ、実際よりも偉大な者であると信じ込ませたのはファースなのだから。彼がそそのかさなかったら、どうなっていたかわからない。ガレスは試そうともしなかったかも知れない。
ガレスは激しく怒りながら彼のほうを向いた。やっと自分の怒りを向ける相手を見つけた。そもそも、ファースこそ自分の父を殺した張本人だ。この馬舎の愚かな少年がこの一連の混乱に自分を巻き込んだのだ。今となっては自分はできそこないの、マッギルの後継者の一人となっただけだ。
「お前なんか嫌いだ」ガレスは怒りで煮えくり返った。「お前の言った約束が今ではどうだ?私が剣を振りかざすだろうと言った確信は?」
ファースは緊張に息を呑んだ。言葉もなかった。何も言うことがないのは明らかだ。
「申し訳ありません、陛下」彼が言った。「私が間違っていました」
「お前のすることは間違いばかりだ」ガレスが鋭く言う。
確かにそうだ。考えれば考えるほど、ファースがいかに誤っているかを悟るばかりだ。実際、ファースがいなければ父はまだ生きていただろう。そしてこのような騒ぎに巻き込まれることもなかった。王位の重圧が自分にのしかかることも、すべてがうまくいかなくなることもなかったろう。ガレスは、自分が王になる前、父の存命中に過ごしていた平穏な日々が恋しかった。突然、元の状態をすべて取り戻したい衝動に駆られたが、それは不可能だった。何もかもすべてファースのせいだ。
「ここで何をしている?」ガレスが詰問する。
ガレスは明らかに緊張した様子で咳払いをした。
「えっと、召使たちが話していて・・・噂を聞いたものですから。ご兄弟があちこちで聞きまわっていると、耳に入ってきて。召使たちの働くところで、凶器を見つけるために汚物の落とし樋を探っているのが目撃されたって。父君を刺すのに使った短剣です」
その言葉にガレスは全身が冷たくなり、衝撃と恐怖で凍り付いた。これ以上ひどい日があろうか?
彼は咳払いをした。
「彼らは何を見つけたんだ?」ガレスが尋ねた。喉が渇き、ことばがうまく出てこない。
「わかりません、陛下。何か疑っているということしか」
これ以上深まることなど予想できなかったガレスのファースへの憎しみが一層強くなった。彼のへまさえなければ、凶器をきちんと始末してさえいれば、このような状況に置かれることもなかった。ファースのせいですきができてしまった。
「一度しか言わない」ガレスがファースに詰め寄り、これ以上はないほどの怖い顔で言った。「お前の顔など二度と見たくない。わかったか?私の前に二度と現れるな。お前を遠く離れた場所へ追放する。そしてこの城の敷居を再びまたぐことがあれば、お前を逮捕させる。」
「さあ、行け!」ガレスが叫んだ。
ファースは目に涙をため、振り向いて部屋から出て行った。廊下を駆けていく足音がずっとこだましていた。
ガレスは再び剣と儀式の失敗に思いをめぐらせた。自分で災難の口火を切ってしまったような気がしてならなかった。崖っぷちへと自分で自分を追い込み、ここから先は下降の一途をたどるだけのように感じられた。
父の部屋で、静けさの中に根が生えたように立ち尽くし、震えていた。自分が一体何を始めてしまったのかと考えながら。これほど孤独を感じ、自信を喪失したことはなかった。
これが王になるということなのか?
*
ガレスは石造りのらせん階段を早足で上り、次の階へ、城の最上階の胸壁へと急いだ。新鮮な空気が必要だった。考える時間と場所が。宮廷、臣民を見渡し、それが自分のものであることを確かめる王国で最高の場所が。悪夢のような一連の出来事があった後もなお、自分がいまだ王であることを確かめるための。
ガレスは従者たちも退け、たった一人で踊り場から踊り場へと、息を切らして走り続けた。一回だけある階に立ち寄り、身をかがめて息をついた。涙が頬を伝った。自分を叱る父の顔が、いたるところで目の前に浮かんだ。
「あなたなんか嫌いだ!」宙に向かってガレスは叫んだ。
嘲けるような笑いを確かに聞いたような気がした。父の声だ。
ガレスはここから逃げたかった。振り返り、走り続けてやがて最上階に着いた。扉から走り出ると、新鮮な夏の空気が顔に当たった。
深呼吸をして息をつき、太陽の光とあたたかい風を浴びた。父の王衣を脱ぎ、地面に投げ捨てた。暑くて、まとっていたくなかった。
胸壁の端に行き、城の壁につかまった。荒い息で宮廷を見下ろした。切れることのない人の波が、城から出て行く。儀式、自分の儀式が終わって帰る者たちだ。彼らの落胆がここからでも感じられた。誰もが小さく見える。皆が自分の支配下にあることに驚くばかりだった。
だが、それはどれくらい続くのだろう?
「王であるというのはおかしなものよ」老人の声がした。
ガレスは振り向いて驚いた。アルゴンがほんの数歩先に立っていた。白い外套と頭巾を身に着け、杖を手にしている。彼は口元に笑みを浮かべてガレスを見た。目は笑っていなかった。輝きを持った目がまっすぐに向けられ、ガレスは追いつめられた。多くを見抜く目だ。
アルゴンに言いたいこと、尋ねたいことはガレスには山ほどあった。だが、剣を振ることに失敗した今、それらの一つたりとも思い出せなかった。
「なぜ教えてくれなかったのだ?」ガレスは絶望を声ににじませながら聞いた。 「私が剣を振りかざすよう運命づけられていないと伝えることもできたであろう。恥を防ぐことも」
「私がなぜそうしなければならない?」アルゴンが尋ねた。
ガレスが睨み付ける。
「そなたは真の王の相談役ではない」ガレスが言った。「父の相談役は務めようとしていた。が、私にはそうしない」
「お父上は真の相談役を持つにふさわしかったからではないかな」アルゴンが答えた。
ガレスは怒りを募らせた。この男が憎くて、非難した。
「そなたは私には必要ない」ガレスが言った。「父が雇った理由はわからないが、宮廷にそなたはもう要らない」
アルゴンが笑った。虚ろで、怖ろしい声だった。
「お父上は私を雇ったりなどしておられない。愚かな者よ」彼が言う。「その先代のお父上もだ。ここにいるのが私の運命なのだ。実際には、私が彼らを雇ったのだ」
突然、アルゴンは一歩踏み出すと、魂を見抜くようにガレスを見た。
「同じことがそなたにも言えるだろうか?」アルゴンは尋ねる。「そなたもここにいるよう運命づけられているのだろうか?」
その言葉はガレスの痛いところを突き、ぞっとさせた。それこそ、自分でも考えていたことだった。これは脅しではないかと思った。
「血によって君臨する者は、血で支配する」アルゴンはそう告げると、素早く背を向け、歩き始めた。
「待ってくれ!」ガレスが大声で言う。アルゴンを行かせたくなかった。答えが欲しい。「それはどういう意味だ?」
ガレスには、自分の統治が長くは続かないというメッセージをアルゴンが伝えているように思えてならなかった。アルゴンが言いたかったのはそのことか、知る必要があった。
ガレスはアルゴンを追った。だが、近づいた瞬間、目の前でアルゴンが消えた。
振り返って周囲を見回したが、何も見えなかった。どこかで虚ろな笑い声が響くだけだった。
「アルゴン!」ガレスは呼んだ。
もう一度振り返り、天を仰いだ。そして片膝をつき、頭をのけぞらせて甲高く叫んだ。
「アルゴン!」
第七章
エレックは大公、ブラント、そして数十名の大公の側近たちと並んで、サバリアの町の曲がりくねった道を進んだ。一行が召使の少女の家へと向かう間、群衆が溢れ出てきた。エレックが少女にすぐにでも会いたいと申し出て、大公が個人的に案内をしたのだった。大公が行くところにはどこにでも人々がついていった。エレックは膨らみ続ける側近の一団を見回し、少女のところへ大勢の人間を従えて行くことになり困惑していた。
初めて彼女を見て以来、エレックは他のことが考えられなかった。この少女は一体誰なのだろう、と彼は思った。気高く見えるにもかかわらず、大公の屋敷で召使として働いている。なぜ自分からあんなにあわてて逃げたのだろう?長年、王族の女性たちにもすべて出会いながら、この少女だけが自分の心をとらえたのはなぜだろう?
これまで王族たちに囲まれて生きてきて、自分も王の息子であるため、他の王族も一瞬にしてそうと見分けることができた。そして彼女を見つけた瞬間、今よりもずっと高い身分の者だと感じ取ったのだった。彼女が誰なのか、どこから来たのか、ここで何をしているのか知りたくて好奇心でうずうずしていた。もう一度この目で見て、自分が想像しているだけなのか、再び同じ感覚を持つのか、確かめる必要があった。
「召使たちは、少女が市の郊外に住んでいると教えてくれました」大公が歩きながら説明する。一行が進むのを、道の両側で人々がよろい戸を開けて見ていた。大公と側近たちが普通の道に現れたことに驚いた様子だった。
「見たところ、彼女は宿屋の主人の召使のようです。出自、どこから来たかは誰にもわかりません。ある日この市にやって来て、宿屋で年季奉公に入ったということしかわからないのです。彼女の過去は謎のようです」
一行はまた別の横道に曲がった。進むにつれ、敷石は一層歪み、小さな家々は密集してどんどん傾いたものになっていく。大公は咳払いをした。
「私は特別な行事のときだけ彼女を召使として雇いました。静かで人付き合いを避けています。誰も彼女のことはあまりよく知らないんですよ、エレック」大公はやがてエレックのほうに向き直り、その手首に手を置いて言った。「本当によろしいのですか?誰であったとしても、この女性はただの平民です。あなたには王国のどの女性でも選ぶことができるのですよ」
エレックは同様の真剣さで大公を見つめた。
「私はこの少女にもう一度会わねばなりません。誰であっても構いません」
大公は賛成しかねる様子で首を振った。一行は歩き続け、道を何度も曲がり、狭く曲がりくねった路地を通って行った。サバリアのこの一角は更にみすぼらしい様相を呈してきた。道端には酔っ払いが溢れ、汚いものが散らかり、鶏、野良犬がそこらじゅうを歩き回っていた。酒場を幾つも通り過ぎ、常連客の叫びが外に響く。一行の前で何人もの酔っ払いがよろめいていた。日没とともに、道にはたいまつがともされた。
「大公に道を開けるのだ!」侍従長が叫びながら前に走り出て、酔っ払いを脇に押しのけた。道端ではどこも、いかがわしい者たちが道を開けて、大公がエレックを連れて通り過ぎて行くのを驚いて見守っていた。
一行はついに小さい、粗末な宿屋に到着した。しっくい造りの建物で、スレート葺きの屋根が傾斜している。下の酒場には50名ほどの客を、上の階では数名の宿泊客を収容できるようだ。 正面の扉は歪み、窓は一枚割れている。入口のランプは曲がって、たいまつはろうが減って点滅していた。扉の前で一行が止まった時、酔っ払いの叫び声が窓から溢れていた。
あのような素晴らしい少女がなぜこのような場所で働いているのだろうか? エレックは不思議に思い、中から漏れてくる叫び声ややじを聞いて怖ろしくなった。彼女がこのような場所で屈辱を耐え忍ばなければならないことを考えると心が痛んだ。 これは間違っている、 エレックはそう思い、彼女を救おうと決心した。
「これ以上ひどいところはないような場所に来て花嫁を選ぼうとなさるのはなぜですか?」大公がエレックのほうを向いて尋ねた。
ブラントも彼を見た。
「これが最後のチャンスだ」ブラントが言った。「城に戻れば王家の血を引いた女性たちが大勢待っているのだぞ」
だがエレックは首を振った。決心が固かった。
「扉を開けよ」エレックが命令した。
大公の家来の一人が走り出て、扉を強く引いて開けた。気の抜けたエールの匂いが漂ってきて、家来はたじろいだ。
中では酔っ払いたちがバーにかがみ込むか木のテーブルに腰かけるかして、大声で叫んだり、互いに押し合いへし合いしては笑ったり、野次を飛ばしたりしていた。腹が出て、ひげは剃らず、服も洗っていない。がさつな人々であることはエレックにもすぐにわかった。彼らは戦士ではない。
エレックは中に数歩入って彼女の姿を探した。あのような女性がこんなところで働くなど想像できなかった。違う場所に来たのではないかと思った。
「すみません、ある女性を探しているのですが。」エレックはそばにいた男に尋ねた。腹が出てひげも剃っていない、背が高くて恰幅の良い男だ。
「で、あんたは?」男はふざけて言った。「来る場所を間違えたんじゃないか!ここは売春宿じゃない。通りの向こう側にはあるがな。みんなぽっちゃりして良い女らしいぜ!」
男はエレックに向かって大声で笑い始めた。仲間も数人それに加わった。
「売春宿を探しているのではない。」エレックはしらけた様子で答えた。「ここで働いている女性だ」
「じゃあ、宿屋の召使のことだろう。」別の大柄な酔っ払いが言った。「多分、奥のどこかで床掃除でもしてるよ。うまくいかねえな、あっしの膝にでも座っててくれたら良いのにな!」
男たちは皆、自分たちの冗談に盛り上がって大声で笑った。エレックは想像して顔が赤くなった。恥ずかしくなったのだった。こんな者たちに彼女が仕えなければならないとは、エレックには考えたくもない屈辱だった。
「それで、お前さんは?」別の声がした。
誰よりも太っている男が前に進み出た。濃い色のあごひげと目、広い顎を持ち、しかめっ面をして、みすぼらしい男たちを数名従えている。脂肪は少なく筋肉質で、明らかに縄張りを示すかのように、威嚇的にエレックに近づいた。
「私の召使の少女を盗もうとしているのかね?」と詰問する。「そういうことなら表に出な!」
男は一歩前に出て、エレックをつかもうと手を伸ばした。
だが、長年の訓練で鍛え上げられている、王国で最も偉大な騎士エレックは、この男の想像をはるかにしのぐ反射神経の持ち主だった。男の手がエレックに触れた瞬間、エレックは行動に移した。男の手首をつかむと電光石火のごとく相手を回転させ、シャツの背をつかんで部屋の反対側まで押しやった。
大男は砲弾のように飛んで行き、数名の他の男たちも道連れにして、全員がボーリングのピンのように狭い部屋の床に倒れた。
店内がすっかり静まり返った。誰もが動きを止めて見ていた。
「戦え!戦え!」男たちが唱える。
宿屋の主人はぼう然として足がよろめき、叫びながらエレックに突進してきた。
今度はエレックも待ってはいない。攻撃に応戦すべく前に進み出て、腕を上げ、相手の顔にまっすぐ肘鉄をくらわせた。鼻がへし折れた。
彼は後ろによろめき、床にうつ伏せに倒れた。
エレックは前に出て、その大きさをものともせず相手をつかみ上げて頭の上に持ち上げ、数歩前進してから投げ飛ばした。男は宙を飛び、店内の半分の人間も共倒れとなった。
誰もが凍り付いた。野次も止んで、すっかり静かになり、誰か特別な者がここに来たのだとわかったようだった。だがバーテンダーが、突然ガラスの瓶を頭の上に持ち上げ、エレック目がけて走って来た。
エレックはそれを見て既に自分の剣に手をかけていた。剣を引く前に隣にいた友人のブラントが前に出てベルトから短剣を抜き、その切っ先をバーテンダーの喉に突き付けた。
バーテンダーは正にそこに向かって来て、止まって凍り付いた。短剣が彼の皮膚を突き破るところだった。恐怖に目を見開き、冷や汗をかいて、瓶を宙にかざしながら止まっていた。周囲はピンが落ちる音さえ聞こえそうなほど静まり返った。
「瓶を離せ」ブラントが命令する。
バーテンダーが言われたとおりにすると、瓶が床に落ちて割れた。
エレックが金属音を響かせて剣を抜き、床でうなっている宿屋の主人のところに歩み寄ると、剣を喉に突き付けた。
「一度だけしか言わない。」エレックが言った。「この者たちを店からすべて退去させなさい。今すぐにだ。あの女性と二人きりにしてほしい」
「大公だ!」誰かが叫んだ。
全員が振り向き、やっと、家来たちに囲まれて入口のそばに立っている大公の存在に気付いた。皆が帽子を取り、お辞儀をした。
「私が話を終えるまでに店を空にしないと」大公が告げた。「全員を直ちに投獄する」
店内が狂乱状態になり、男たち全員が店を明け渡す大公のそばを通り過ぎ、正面のドアから外に出ようとした。飲みかけのエールの瓶もそのままだった。
「お前もだ」ブラントはバーテンダーに向かってそう言うと、短剣を下げ、彼の髪をつかんでドアのほうへ押しやった。
ほんの少し前まで騒々しかった店内が、今はエレック、ブラント、大公と数十名の側近たちを除いて誰もいなくなり、静かになった。背後で音を立てて扉を閉めた。
エレックは床に座って今もぼう然と鼻の血をぬぐっている宿屋の主人に向き直った。 エレックは彼のシャツをつかみ、両手で彼を立ち上がらせて、空いたベンチの一つに座らせた。
「今夜一晩の商売をあんたは台無しにしたな。」主人は哀れな声を出した。「このつけは払ってもらうよ」
大公が歩み出て彼を手の甲で叩いた。
「この方に手を出そうものなら、お前を死刑に処することもできるのだぞ。」大公が厳しく言った。「この方がどなたか存じ上げないのか?国王の最高の騎士、シルバーのチャンピオン、エレック様だぞ。その気になれば、この方がお前を今この場で殺すこともできる」
宿屋の主人はエレックを見上げ、初めて本当の恐怖が彼の顔をよぎった。座ったまま震えそうだった。
「まったく存じ上げませんでした。あなた様がおっしゃいませんでしたので」
「彼女はどこだ?」エレックがもどかしげに尋ねた。
「奥で台所の掃除をしております。あの娘とお会いになりたいっていうのは一体どういうことなんで?何かあなた様のものを盗んだりしたんでしょうか?あの娘はただの年季奉公の召使ですが」
エレックは短剣を抜き、男の喉に突き付けた。
「彼女を今度召使と呼んだら」エレックが警告する。「私がお前の喉をかき切るぞ。わかったな?」男の皮膚に刃を当てながらエレックがきつく言った。
男は目に涙をためて、ゆっくりと頷いた。
「彼女をここに連れて来なさい。急いで」エレックはそう命じ、彼を引っ張って立ち上がらせ、体を押した。男は店内へ、そして奥の扉へと飛ばされた。
宿屋の主人が行ってしまうと、扉の向こう側から鍋のぶつかる音や抑えた怒鳴り声が聞こえた。その後すぐに扉が開き、数人の女性たちが出てきた。皆、台所の油だらけのぼろ布のドレスやスモックを身に着け、帽子をかぶっている。 六十代の年配の女性が三人いた。エレックは、自分が誰のことを言っているのかこの男はわかっているのだろうか、といぶかった。
その時、彼女が出てきた。エレックは心臓が止まりそうだった。
息ができないほどだった。この女性だ。
油のしみがついたエプロンを着け、目を上げるのが恥ずかしい様子で顔を下に向けたままだ。髪は結んで布で覆っている。頬には泥がこびりついているが、それでもエレックは彼女にぞっこんだった。皮膚は若々しく完璧な美しさで、頬が高く、顎も彫刻のようだ。鼻にはそばかすがあり、唇が厚い。額は広く、威厳がある。そして美しいブロンドの髪が帽子からあふれ出ていた。
目を上げて一瞬だけ彼の方を見た。大きな、美しいアーモンド形の緑色の瞳は光で、澄んだ青へと変化し、またもとの色へ戻った。エレックはその場にくぎ付けになった。最初に会った時よりも一層心を奪われていることに自分でも驚いた。
彼女の後ろでは、宿屋の主人が鼻の血を今も拭いながら、しかめっ面で出てきた。少女は年配の女性たちに囲まれて、エレックのほうに向かい恐る恐る前に進み出た。近くまで来ると膝を曲げてお辞儀した。エレックは身を起して少女の前に立ち、大公の側近たちもそれに従った。
「ご主人様」少女は優しく、穏やかな声をそう言い、エレックの心を満たした。「私がなぜご機嫌を損ねてしまったのかお教えください。自分ではわかりませんが、大公閣下のお屋敷に行くために私のしたことが何であれ、申し訳ございませんでした」
エレックは微笑んだ。彼女の言葉づかい、声、どれも気分を回復させるような気がした。話すのをやめてほしくなかった。
エレックは手を伸ばして彼女の顎に触れ、その優しい目が自分の目と合うよう顔を上げさせた。その目に見入ると彼の心臓は高鳴った。まるで海の青さに溺れてしまうようだった。
「あなたは怒らせるようなことは何もしていません。あなたには人を怒らせるようなことはできないと思います。ここへは怒りではなく、あなたを思う気持ちのために来ました。あなたに会った時から、他のことが考えられなくなってしまいました」
少女は狼狽して、瞬きを何度もしながらすぐに目を床に落としてしまった。手をねじり、圧倒され緊張した様子だった。このようなことに慣れていないのが明らかだ。
「お願いです、教えてください。あなたのお名前は何と言うのですか?」
「アリステアです」少女はつつましく答えた。
「アリステア」エレックは感動しながら繰り返した。これまで聞いたなかで最も美しい名前だと思った。
「ですが、なぜそんなことをお知りになりたいのかわかりません」彼女が床を見つめながら小さな声で聞いた。「あなた様は貴族でいらっしゃいますが、私はただの召使です」
「正確に言うと、その娘は私の召使だ」宿屋の主人は進み出て意地悪くそう言った。「私のところに年季奉公に入ったんですよ。何年か前に契約を交わしました。約束は7年です。それと引き換えに、私が食べ物と住む場所を世話してやっているんです。3年目に入ったところですよ。ですから、こんなこと全部時間の無駄です。この娘は私のものです。私の所有です。連れて行くことなんかできませんよ。おわかりいただけましたか?」
エレックはこれほど人を憎んだことはないくらい、この宿屋の主人に対して憎しみを抱いた。剣を抜き、心臓を突き刺して始末してしまいたい思いがよぎった。だが、いかにそうされて当然の男であっても、エレックは王の法律を破る気にはなれなかった。自分の行動は国王に影響を及ぼすからだ。
「王の法律は王の法律だ」エレックは毅然として男に言った。「それを破ろうとは思わない。それだけは伝えた。明日はトーナメントが始まる。私は他の男と同じく、花嫁を選ぶ権利がある。ここで今、私がアリステアを選ぶことを知らせておく」
部屋中に息を呑む声が広がった。皆が衝撃に互いの顔を見合わせた。
「それは」エレックが付け加えて言った。「彼女が承諾すればだが」
エレックはアリステアがずっと下を向いたままなのを見て、胸が高鳴った。彼女の頬が赤らんでいるのがわかった。
「承諾してくださいますか?」エレックが尋ねた。
店内が静まり返った。
「ご主人様」彼女が静かに言った。「あなた様は私が誰なのか、どこから来たのか、何もご存じありません。そして、私はそうしたことをお話しできないのです」
エレックが不思議そうな顔をして見つめ返した。
「なぜ話せないのですか?」
「ここへ到着してから誰にも話しておりません。私は誓いを立てたのです」
「それは一体なぜなのですか?」エレックは興味をそそられ、問いただした。
アリステアは黙って下を見ているだけだった。
「それは本当です」女中の一人が口を差し挟んだ。「この人は自分が誰なのか話したことがないんですよ。なぜここにいるのかも。話すのを拒むんです。何年も聞こうとしているんですがね」
エレックは非常に不可解な気がした。だが彼女の神秘性が一層深まっただけだった。
「今、誰だかわからないのであれば、知らなくてよいです」エレックが言った。「私はあなたの誓いを尊重します。ですが、そのことで私の気持ちが変わることはありません。あなたが誰であろうと、このトーナメントに勝った時は私はあなたを選びます。王国中のすべての女性のうちからあなたをです。もう一度伺います。受けてくださいますか?」
アリステアは床に目を落としたままだった。そしてエレックの目の前で、彼女の頬を涙が伝った。
突然、アリステアは振り向いて部屋から走って出て行き、背後の扉を閉めた。
エレックは他の者たちともども、驚きに言葉をなくして立ちすくんだ。彼女の反応をどう解釈したらよいのかわからなかった。
「これであなた様も私も時間を無駄にしたことがわかりましたね。」宿屋の主人が言った。「あの娘はノーと言った。ですからもう出て行ってくださいよ」
エレックはしかめっ面を返した。
「ノーと言ったわけじゃない」ブラントが口をはさんだ。「返事をしなかっただけだ」
「時間をかける権利がある」エレックは彼女を弁護した。「考えるべきことはたくさんあるのだから。私のことも知らないわけだし」
エレックは何をすべきか、その場で熟考した。
「私は今晩ここに泊まることにする。」エレックは最終的にそう言った。「ここに部屋を取ってくれ。彼女の部屋から離れた廊下の奥に。朝になったら、トーナメント前にもう一度尋ねる。もし承諾してくれれば、そして私が勝てば、彼女は私の花嫁になる。もしそうなれば、奉公人の身請けをする。彼女は私と共にここを離れることになろう」
О проекте
О подписке